NHKの恐竜超世界2で登場した最近見つかった恐竜、マイプ。爪も長くて大きな体をしていました。そんな強そうな恐竜のマイプを徹底解説していきます!
マイプとは?その学名と由来

マイプ・マクロソラックスは、メガラプトル類に属する新種の大型獣脚類です。学名の Maip はパタゴニア伝説に登場する「冷たい風で凍死させる悪霊」の名前で、macrothorax は「大きな胴体」を意味します
化石の発見と産出地
アルゼンチン・サンタクルス州エルカラファテ近郊のチョリロ層(白亜紀後期:約7,000万年前)から発見されました。発掘されたのは背骨、肋骨、烏口骨など。発見範囲は縦3m・横5m・深さ1mほどの露頭に及び、非常に保存状態が良好です。
特徴まとめ:大きさ・体格・爪の構造
- 全長は約9〜10メートル、体重約5トン、幅約1.2メートルのがっしりとした体格を持つ、南半球で当時最大級の肉食恐竜でした。
- 前肢の2本の指に長さ30〜40センチもの鋭く湾曲した大きなかぎ爪があり、これがもっとも印象的な特徴とされています。
- 骨は軽量かつ頑丈な構造で、機動性やパワーを両立していたと見られます。
- 名前の由来は、現地パタゴニアの伝説に登場する極寒の悪霊「マイプ」と、「マクロ(大きな)」、「ソラックス(胴体)」から。
- 頭骨は未発見ですが、細長い頭部で多数の歯があったと推定されています。
南米巨大肉食恐竜としての位置づけ
白亜紀前期〜中期には、スピノサウルス類やカルカロドントサウルス類が南半球で食物連鎖の頂点を占めていましたが、彼らは白亜紀中頃に絶滅しました。しかし、マイプが暮らしていた後期には、メガラプトル類が食物連鎖の頂点に立っていたと考えられます。
マイプはその中でも最後期の代表的種とされ、パタゴニアにおける南米のトップ捕食者として君臨していた可能性が高いのです。
生態と食性の想像
- 頑強な胴体と大型鉤爪から、水辺近くの多様な獲物(恐竜、小型竜脚類、魚類など)を斬撃して仕留める半水生あるいは広範囲に移動する狩人だったと想定されます。
- 高度な含気構造を持つ骨格は、呼吸効率が高く、活動能力に優れていたことを示唆します。
- 地域的にティラノサウルス類に相当する存在として、南半球で独自進化を遂げた「パタゴニアの頂点捕食者」だったと考えられます。
なぜ今、注目されるのか?
- 全身に近い標本で新種が報告されるのは珍しく、形態の詳細な比較が可能という意味で科学的意義が高いです。
- また、南米での恐竜相の理解をアップデートし、北半球とは異なる進化パターンを示すメガラプトル類の存在を強く印象づけました。
- 日本では「フクイラプトル」がメガラプトル類として知られていますが、マイプはそのスケールを大きく超える存在です。
まとめ:マイプが示す進化の物語
マイプ・マクロソラックスは、学術的に保存状態の良い史上最大級のメガラプトル類新種として注目されています。「マイプ」の名の通り、“冷たく恐ろしい存在”として南米白亜紀後期の食物連鎖の頂点に君臨していたと考えられています。
この発見は、恐竜研究における地域差(北 vs 南半球)、進化の多様性、そして時代背景の違いを象徴的に表すものであり、まさに恐竜学のドラマが詰まった一例です。


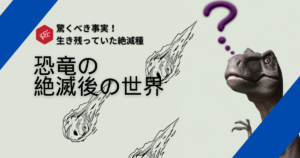
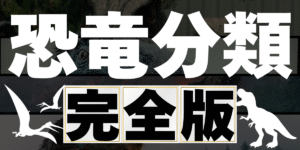

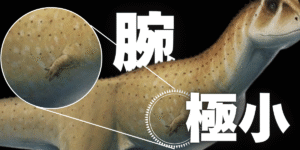
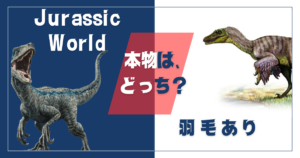
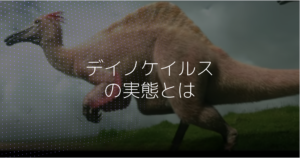


コメント